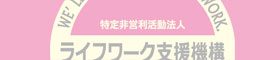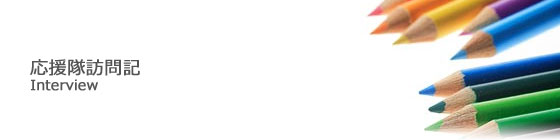
第1回 『師授の魂』 渡邉輝弘氏
記念すべき「応援隊訪問記」第1回目は、宇部商工会議所の専務理事である渡邉輝弘氏(写真:右)に、宇部市の発展と商工会議所の歴史についてお話を伺いました。
聞き手は、同じく宇部商工会議所の宇部地域資源活用促進協議会会長でありインキュベーション・マネージャーである奥谷祐司氏(写真:左)です。

周防灘に面した人口約18万人のまち「宇部」。
沿岸部の工業地帯は瀬戸内工業地帯の一角を担い、空の玄関である空港も擁するまちである。石炭産業で栄え、今日までの道のりを辿ってきた。そして、この大きな時代の波と共に歩んだ先人達には、宇部の百年の計があったという…
時は平成19年、宇部商工会議所の一室。
宇部の歴史において中核となった企業、宇部興産での職務を経て、平成13年に宇部商工会議所へ専務理事として着任した渡邉輝弘氏は、徐々に語り始めた。
「専務理事着任の際に、企業人として経験し鍛えられた中から商工会議所の在り方を示したことがある。私はこれまで様々なプロジェクトを推進してきた。商工会議所というものも、宇部という街を元気にしていく一つのプロジェクトであると思う。
プロジェクトをやる際には、『何のためにやるのか?』『アクションによってどうなるのか?』を常に問い、目的と実態が乖離したプロジェクトは早々と止めてしまった方がいい。
現に私が打ち切ったプロジェクトも少なくないがね・・・。」
冒頭にも述べているとおり、そして皆が存じているとおり、わがまち宇部は石炭産業で発展した都市である。
渡邉氏は、この歴史を今一度紐解いて語ってくれた。
「100年前に、宇部が現在までの発展に至るきっかけがあった。石炭産業を中心として発展してきたわけだが、明治6年に日本坑法が施行され、工業資源は国の所有物となることになった。つまりは、これまである程度自由に採掘出来たものに規制が掛かったわけだ。更には、これまで石炭局の役人だった者がこの権利の大半を息子名義で登録し、実質自身のものとして独占したため、一層商売がやり辛くなった。そこで、困り果てた鉱夫達は旧領主の福原芳山氏に相談する。福原氏は、私財にてこの権利を買い戻し、広く石炭の採掘ができるようにした。これに対して鉱夫たちは福原氏に還元しようと斤先料(いわゆる権利金)を支払っていたが、余りにも多くの斤先料の管理に手間が掛かるために、『宇部共同議会』を設立して管理をしたという。」
この買い戻した鉱業権は福原氏の私財が基であるために、本来なら斤先料を福原氏がもらうべきであろうが、彼は共同議会の設立後も、皆が納めた斤先料には手を付けず、この資金を宇部という街の発展に使用していく。
「宇部共同議会はこれらの単なる管理組織ではなく、宇部村民の繁栄を目的とした公益団体だった。第一部に社会事業を第二部に鉱区管理を置いて、宇部において産業発展の支援を行った。そんな中、次は宇部村民の世論統一のための組織『宇部達聰会』が設立された。更には、具体的事業の実現のために『宇部式匿名組合』も設立して、ここから大きく宇部が発展を遂げていくんだ。この匿名組合の頭に『宇部式』と名の付くように、これは本当に宇部独自の方式で、共同義会・達聰会ともに、宇部人が宇部の発展を目指して知恵を絞って作り上げたものなんだ。」
そして、この宇部式匿名組合の事業として明治30年に宇部興産?の基となる『沖の山炭鉱組合』ができる。それからこの匿名組合の事業で宇部新川鉄工所や宇部紡績所等々が生まれてくる。この『宇部式匿名組合』あってのものだが、これは真に特殊なスタイルで、平たく言えば頭取であるものが一切の責任を負い、出資者には出資以外のリスクはないというものだ。そして、この頭取を務めた人物が『渡邊祐策』である。彼の陣頭指揮のもと街全体で連携して宇部は大きな産業発展を向かえる。まさしく、『共存同栄』社会の出現である。
「ある程度宇部が栄えてきた頃に、渡邊祐策は部下である『俵田明』と『中安閑一』を新規事業模索のための旅に出させた。その時に渡邊祐策は彼らに「石炭等の資源は有限であり、有限である以上いつかは無くなる。百年後の宇部が生き残るために何か見つけ出して来い」と申し伝えたという。そして、俵田氏は石炭からアンモニア工業へとシフトする方向性を、中安氏はセメント産業を更にブラッシュアップさせる事を見出してきた。これを契機に化学産業とセメント産業が宇部の大きな柱となって、窒素製造、ソーダ工業、油化工業へと工業都市としての礎を築いてきた。知恵を絞って既存の資源から宇部が発展することを目指して様々なものを生み出してきたのが宇部の歴史なんだよ。この間、俵田明と大山剛吉は、石炭乾溜の実現のために宇部の石炭を抱えて二度目の渡欧をする。その際に渡邊翁が二人に贈った詩が『かたしとて思いたゆまば何事もなる事あらじ人の世の中』であり、これが宇部のパイオニア魂となってきたんだ。」
「生き残りを掛けた戦いをするのにリスクは必ず生まれる。これに携わる者がどれだけそのリスクを認識して、回避もしくは解消していく術を見出せるのかが大切だろう。今回のプロジェクトが先人に習って宇部の百年後の起点となるものになればいいな。」
確かに、今あるものを今やっているとおりの繰り返しで物事を進めても、その先に派生するものはない。
このまちは、石炭産業から資源は有限であることに気付く。
そして、その中から無限の技術への昇華を求めて様々な産業がおきる。産業が発展することで人が集まり、商業が発展しその延長線に現在がある。
もしも、百年前の先人達が、先を見据えてなければどうなってあろう…
伝統とは、「コト」や「モノ」ではなく、その精神そのもの、つまりスピリットなのだ。伝統を守るということは、それ自体を守ることではなく、その時のその者が開発を続けていくことなのである。
『宇部地域資源活用促進協議会』の若きリーダーは、このスピリットを今受け継いだ気がした。このプロジェクトに関する大きな希望と不安の中で、宇部の街全体を挙げてのアクションが不可欠だと認識した。
「またいつでも話が聞きたければおいでなさい。」そう言い残して渡邉専務理事は部屋を後にした。
2007/4